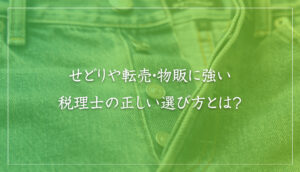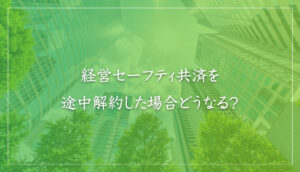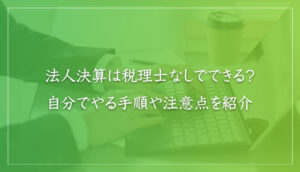少額減価償却資産の特例とは?手続きや注意点も解説|難波の税理士【山本たかし会計事務所】クラウド会計・相談無料
- 山本たかし会計事務所TOP
- コラム
- 会計業務
- 少額減価償却資産の特例とは?手続きや注意点も解説
2025/04/25会計業務
少額減価償却資産の特例とは?手続きや注意点も解説
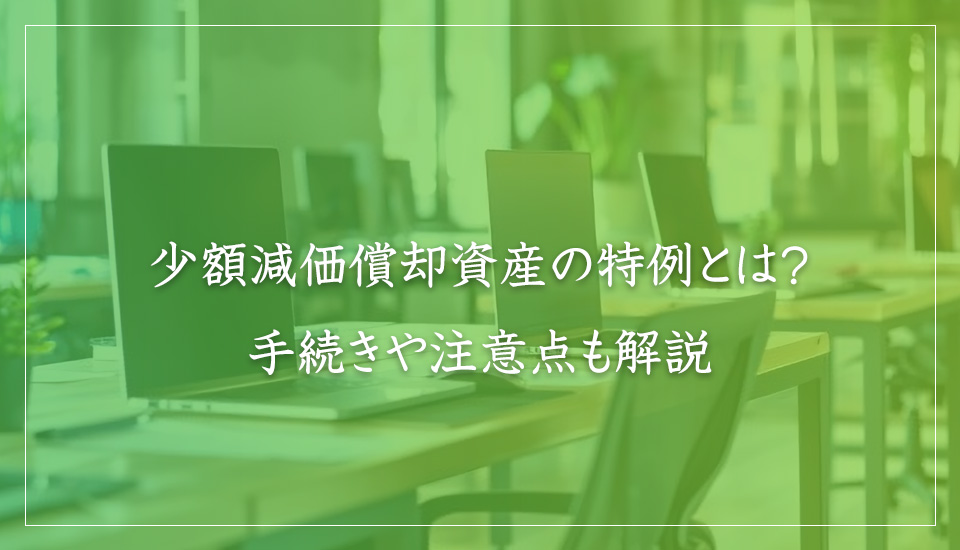
原則として、減価償却資産は耐用年数に応じて費用計上します。
しかし、中小企業等については、税法上、取得価額が低い資産は負担を軽減する規定が別途用意されています。
この記事では、少額減価償却資産の特例について、詳しく解説しています。
減価償却資産とは
事業に使用される建物や附属設備、機械装置、器具備品、車両などの資産は、時の経過や使用によって価値が減少していくことから、耐用年数に応じて費用化していきます。
つまり、取得時にすぐに費用化できるものではなく、何年かにわたって費用化していくようにルールが決められています。
なお、土地や美術品などは時の経過や使用により価値は減少しないと捉えられており、減価償却資産には該当しませんので注意しましょう。
少額減価償却資産の特例とは?
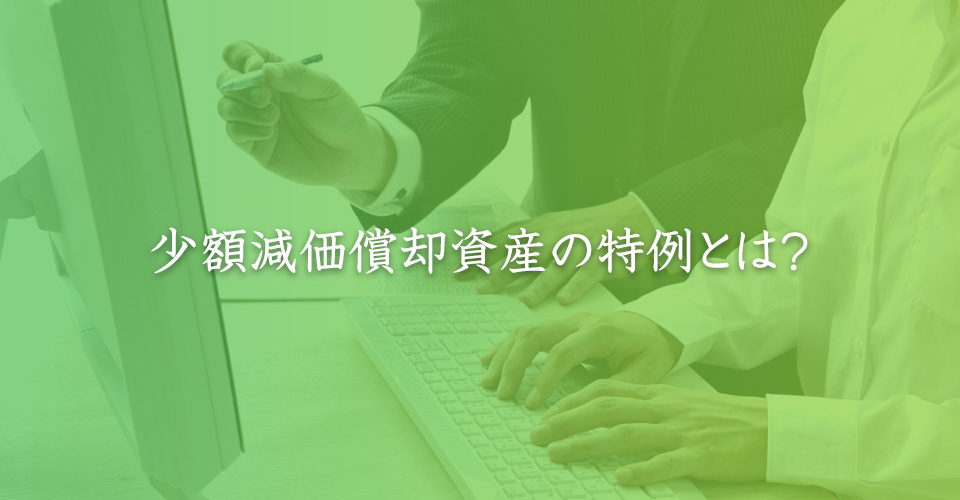
本来、減価償却資産は耐用年数にわたって費用化することになりますが、取得価額が30万円未満である減価償却資産を取得して事業に使用した場合には、一定の要件のもとに、その取得価額に相当する金額を、即時に全額経費にできるという特例があります。
誰が使える?
この特例を使うことができるのは「中小企業者等」です。
中小企業者等とは、従業員数が500人以下であり、資本金または出資金の額が1億円以下の青色申告法人で、連結法人でない法人が適用できます。
また、青色申告の個人事業主についても適用できます。
対象となる資産は?
少額減価償却資産の特例の対象となるのは、取得価額が30万円未満の減価償却資産です。
器具や備品、機械装置等の有形減価償却資産のほか、ソフトウェアや特許権、商標権等の無形減価償却資産も対象となります。
また、所有権移転外リース取引の場合の賃借人が取得したとされる資産や中古資産であっても対象となります。
特例の適用に必要な手続き
少額減価償却資産の特例は、その事業年度において「損金経理」を行っておくことが要件となっています。
つまり、その取得価額全額を費用として計上しておかなくてはいけません。
また、申告の際、法人の場合は法人税の確定申告書に、別表16(7)と適用額明細書を添付して申告することが必要です。
個人事業主の場合には、青色申告決算書の減価償却費の計算の摘要欄に「措法28の2」と記載しましょう。
特例を適用する際の注意点
重複適用できない
この特例の適用を受ける資産は、租税特別措置法上の特別償却や税額控除、圧縮記帳と重複適用ができません。
特別償却や税額控除は、中小企業者等が一定額以上の機械装置等を取得した場合に認められるもので、どちらかを選択適用する制度です。
また、圧縮記帳は、補助金等を受け取って固定資産を取得した場合に、その取得価額から補助金相当額を減額して、補助金等にかかる税金を繰延べる制度です。
これらの制度は、減価償却資産にかかる特別措置であるため、少額減価償却資産の特例と併用することはできませんので注意が必要です。
上限300万円まで
ひとつの事業年度における少額減価償却資産の取得価額の合計額は300万円まで、という上限があります。
300万円を超えたものから通常の減価償却を行うことになります。
次のような減価償却資産を特例の適用対象にしていないか、確認してみましょう。
①や②は特例を適用しなくても費用化できます。
①10万円未満の場合
10万円未満または使用可能期間が1年未満の減価償却資産を取得した場合は、特例を適用するまでもなく、全額経費に計上することができます。
消耗品費、などで経費計上することが一般的です。
これはすべての企業が対象で、白色申告・青色申告か、も問いません。
②20万円未満の場合
10万円以上20万円未満の減価償却資産を取得した場合は、耐用年数に関わらず3年間で均等償却できる方法があり、この方法を適用する資産を一括償却資産と呼びます。
一括償却資産は、特例のような要件を満たす必要はなく、また一括償却資産は「償却資産税」の対象外であることは大きなメリットです。
なお、一括償却資産は途中で廃棄しても除却損は計上できません。
税込・税抜経理?
30万円未満かどうか、といった取得価額の判断は、消費税の「税込経理方式」か「税抜経理方式」か、で異なります。
税込経理の場合は税込金額で、税抜経理の場合は税抜金額で判断します。
例えば、税抜290,000円(税込319,000円)の減価償却資産を購入した場合、税抜経理では290,000円のため特例を適用できますが、税込経理では319,000円となり、特例の適用はできないことになります。
消費税の経理方式を確認し、判断に注意しましょう。
まとめ
少額減価償却資産の特例について解説しました。
10万円未満の減価償却資産、一括償却資産、少額減価償却資産の特例を状況に応じて活用すると良いでしょう。