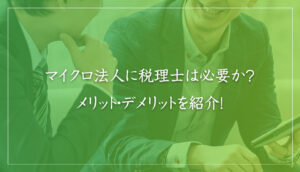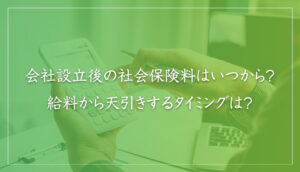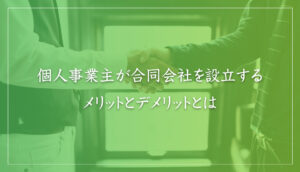マイクロ法人で社会保険料を軽減できる?|難波の税理士【山本たかし会計事務所】クラウド会計・相談無料
- 山本たかし会計事務所TOP
- コラム
- 会社設立
- マイクロ法人で社会保険料を軽減できる?
2025/05/09会社設立
マイクロ法人で社会保険料を軽減できる?
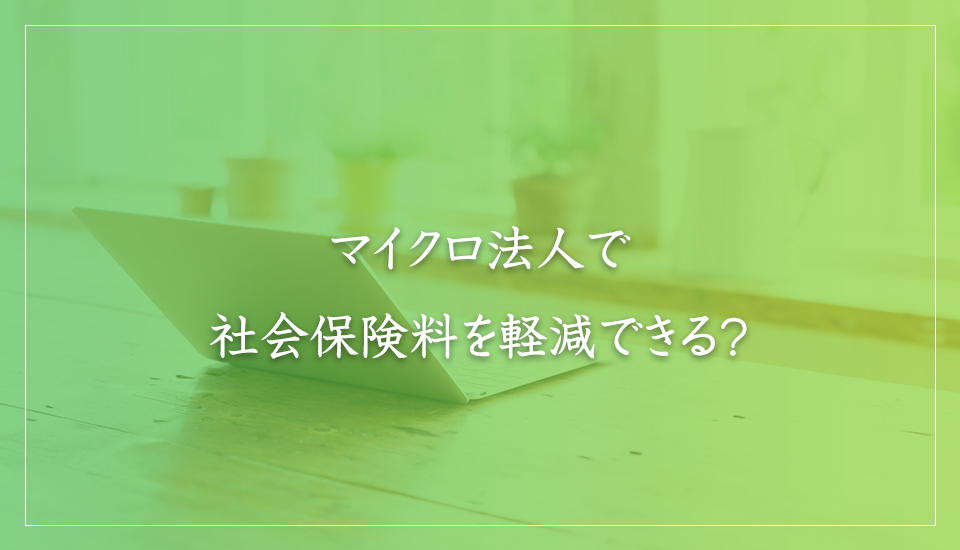
マイクロ法人を設立すると社会保険料の負担を減らすことができる、と聞きます。
本記事ではどのように社会保険料を軽減できるのか、役員報酬との関係、節税なども併せて解説します。
マイクロ法人とは
マイクロ法人とは、簡単にいえば一人会社です。
一人で出資・設立し、一人で経営を行います。
一般的な会社は、事業を拡大して利益追求を目的としていますが、マイクロ法人は、適度な利益を得つつ、個人の社会保険料や税金の軽減を目的としている場合が多いようです。
とはいえ、仮装・隠ぺい、不合理な所得の分散は税法において認められないため、法人事業と個人事業を併用する場合に事業区別が合理的かどうか等、会計・税法に関する細心の注意が必要です。
恣意的とみなされると税務調査のリスクもあります。
マイクロ法人の設立
個人事業主よりも設立時の手続きが複雑
マイクロ法人は、「法人」であるため、設立は会社法に則った手続きが必要です。
定款の作成や法人登記、税務署など関係各所への届出を行うことになります。
株式会社設立の場合、公証役場で定款の認証を行わなければならず、数万円の認証手数料と謄本手数料がかかります。
合同会社設立の場合は不要です。
また、法人登記の際は登録免許税(株式会社で15万円、合同会社で6万円)がかかります。
申告や法人税の負担
法人を設立すると、決算期には法人税の申告・納税が必要です。
個人事業主も毎年確定申告を行いますが、法人の決算は所得税の確定申告よりも煩雑で、会計・税法の知識がより必要とされます。
また、社会保険に関する手続きなども発生します。
会社員は設立できるか?
会社員も法人を設立することは可能ですが、勤務先の会社によっては副業を禁止している場合もあるため就業規則や雇用契約を確認しましょう。
なお、社会保険については会社で成立しているため社会保険料負担の削減メリットはありません。
どうやって削減できるの?
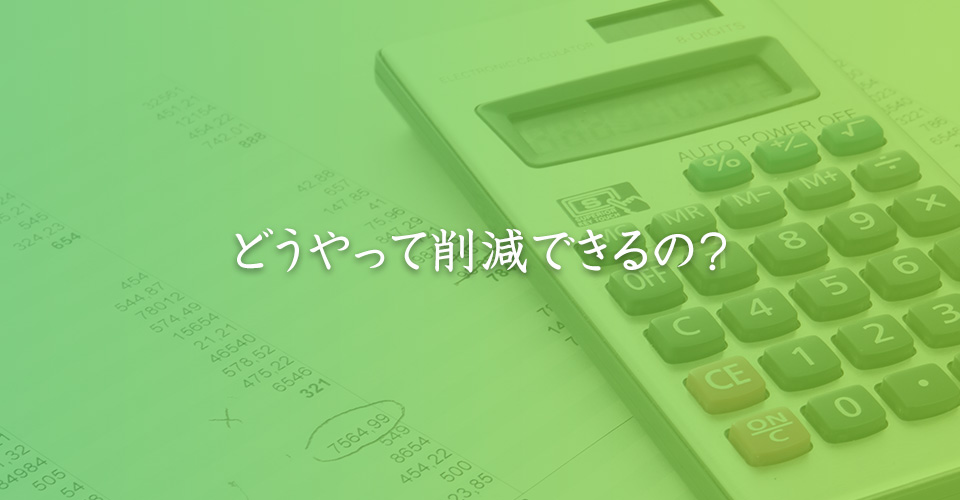
扶養家族分の保険料
個人事業主の場合、国民健康保険・国民年金に加入しますが、マイクロ法人を設立すると、社会保険の加入対象となることができます。
社会保険は国民健康保険・国民年金と違い、被扶養者が何人いても保険料は増加しません。
被扶養者が多い人はお得といえるでしょう。
役員報酬を低額にする
社会保険料は、給与の額に基づいた「標準報酬月額」によって決定されます。
給与が高いほど社会保険料の負担が増加し、給与が低ければ負担は少なく済みます。
つまり個人事業主で所得が高い場合、国民健康保険・国民年金の負担が重くなりますが、マイクロ法人を設立し、自分の役員報酬を低く設定すれば、社会保険料の負担を抑えることができるのです。
ただし、社会保険料の負担は抑えることができますが、将来的には年金受給額が減ることなど、長期的な影響があることは留意しましょう。
社保以外のメリット
個人事業主から法人化すると、取引先や金融機関などからの社会的信用度が高まるメリットがあります。
また、個人事業主で所得が高い場合、所得税は累進税率であることから税負担が重くなりやすく、法人税率の方が有利になる場合があります。
また、法人は個人事業主よりも経費の範囲が広いともいわれています(不適切な経費計上は当然認められません)。
役員報酬も経費に含まれ、社会保険料の会社負担分も経費となります。
設立時の手続き
法人設立時には、社会保険加入の手続きが必要です。
健康保険と厚生年金保険
設立日または加入者発生から5日以内に、管轄の年金事務所に届出を行います。
労働保険
労働保険には、労災保険と雇用保険があります。
従業員がいる場合に加入が必要ですが、一人会社の場合には不要です。
保険関係が成立した翌日から10日以内にハローワークに届出を行います。
注意点
法人は、法人税、法人事業税や法人住民税が発生します。
利益がなく、赤字であったとしても法人住民税については納税が必要で、地方によって異なりますが、数万円はかかります。
また、場合によっては消費税や固定資産税などの負担も考える必要があります。
税理士など専門家に依頼すると報酬が発生しますが、手間やリスクを考えると賢明かもしれません。
まとめ
マイクロ法人を設立し、役員報酬を低額に設定すると、社会保険料を軽減することができます。
ただし、法人の設立には費用も手間もかかるうえ、法人税の申告・納税など負担も発生し、経理や税務の知識が必要です。
設立を検討する際はメリットとデメリットを確認し、節税だけにとらわれることがないよう、法令順守に留意しましょう。
また、短期的なメリットだけでなく、老後の生活なども視野に入れて検討する必要があります。